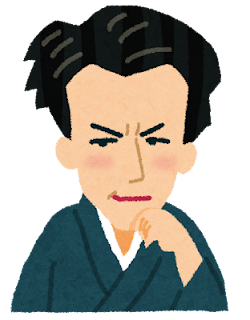令和7年10月改正!マンション標準管理規約(単棟型)の主要ポイント徹底解説(令和8年4月1日施行改正区分所有法反映)

マンション管理組合の皆様、区分所有者の皆様、今回のブログでは、令和8年4月1日に施行される改正区分所有法を反映した、「令和7年改正 マンション標準管理規約(単棟型)」の主要な変更点について、詳細にご紹介します 。 この度の改正は、長年の課題であった所有者不明者や管理不全への対策を強化するとともに、管理組合の意思決定の円滑化を図るための、非常に重要なアップデートとなっています。是非、最後までお読みください。 -------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ.所有者不明・管理不全対策(理事会権限の強化) 法改正に伴い、管理組合が所有者不明や管理不全の専有部分に対して、より迅速かつ適切に対応するための手続きが明確化されました 。 1. 所在不明者の総会除外(第67条の3新設) 所在等が不明な区分所有者を総会決議から除外するための手続きが明確化されました 。理事会の決議を経て裁判所に請求できる手続きが定められており、意思決定の円滑化を図ることができます。 2.所有者不明専有部分の管理(第67条の4新設) 所有者不明専有部分の管理命令を裁判所に請求する際、理事会の決議が必要となります。これにより、管理費滞納といった問題に管理組合として組織的に対処することが可能となります。 3.管理不全専有部分の管理(第67条の5新設) 悪質な居住環境維持不全に対処するため、管理不全専有部分の管理命令を裁判所に請求する際も、理事会の決議が必要と定められました。 -------------------------------------------------------------------------------- Ⅱ.総会運営の適正化 総会の成立要件や決議要件が変更され、管理組合の意思決定のあり方が見直されました。 4.総会成立の定足数変更(第47条第1項) 総会の成立要件が、「議決権総数の半数以上」から、**「議決権総数の過半数」**に出席要件が変更されました。 5.特別決議の定足数追加(第47条第3項) 規約改正など(特別多数決議)を行う際の定足数に、新たに**「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数」**の出席要件が追加されました。決議自体は、引き続き出席組...